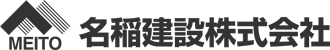- HOME
- コラム
コラム
-
【保存版】注文住宅 ご相談から引き渡しまでの流れをご紹介
- 投稿日

注文住宅を建てるまでは、どのような流れになるのでしょうか。
「注文住宅はどのような流れで建てるのか」
「どれだけの期間がかかるのか」
「ハウスメーカーや工務店はどう選ぶのか」
「建築代金の支払いの仕組みはどうなっているのか」今回は、このような悩みを解決できるような内容を紹介していきます。
この記事を読むことで、以下の内容が理解できます。
・注文住宅のご相談から引き渡しまでの期間及び流れ
・ハウスメーカーや工務店の選び方
・建築代金の支払い方法注文住宅のご相談から引き渡しまでの期間及び流れ
・ご相談~設計プランの提案~ご契約:2ヶ月~3ヶ月(土地が購入がない場合、1ヶ月程度で土地が決った場合)
・ご契約~インテリア打ち合わせ~着工:2ヶ月~3ヶ月
・着工~引き渡し:建物の規模・建築条件にもよりますが4ヶ月~5カ月注文住宅の相談から引き渡しまでにかかる期間は、約1年が一般的ですが、設計プランやインテリアプランにこだわりたいという方は、その分打ち合わせ回数が増え、打ち合わせから着工迄の期間が伸び、トータルの期間が伸びることになります。また、延床面積が標準よりも大きい注文住宅の場合、着工から引き渡し迄の期間が伸び、同じようにトータルの期間が伸びます。
引き渡し・入居のご希望の時期がある方は、早めに相談されることをおすすめします。ご相談
・資金計画やプランニング
・ご入居までのスケジュールご相談の段階では、資金計画やプランニング、全体のスケジュールについて、打ち合わせします。プラス重要なのが、「どこに建てるか」という点、希望の土地を見つけるまでに6ヶ月以上、ときには数年かける人もいます。
注文住宅には、住宅を建てる本体工事費用だけでなく、給排水設備などの付帯工事費用、その他の諸経費がかかります。
工事分類
内容
総予算に対する割合
本体工事費用
基礎・構造・設備工事
75~80%
付帯工事費用
ガス・給排水・外構工事
15~20%
諸経費
申請費用・税金
5~10%
参考:注文住宅の費用や相場 大工が教える失敗しない家づくり(https://ie-daiku.org/souhiyou.html)
それぞれの内訳は上記のようになっているので、計画している総予算をこの割合で振り分けて、計画そのものに妥当性があるかどうかを計算してみてください。
例えば、岐阜県の注文住宅の相場は約3,228万円(建物のみ)です。
・本体工事費用(総予算の80%の場合):約2,582万円
・付帯工事費用(総予算の15%の場合):約484万円
・諸経費(総予算の5%の場合):約161万円それぞれの費用に振り分けてみると上記のようになります。
費用の目安として参考にしてみてください。参考:岐阜の注文住宅相場(https://www.housingexhall.com/knowledge/gihu-homeprices.html)
また、住宅ローンの借入額は各金融機関の住宅ローンシミュレーションツールで簡単に調べられるので、予算の参考にすることをおすすめします。
参考:住宅ローンシミュレーション(https://loan.mamoris.jp/)
土地探し
・土地を所有していない場合は土地探し土地探しは一般的に不動産会社へ相談し、希望の立地かつ予算に合う土地を探します。
通勤や通学にかかる時間、スーパーや病院などの周辺環境や日当りの良さ、災害危険区域に入っていないかなど、土地を決める上で検討すべきことはたくさんあります。
ハウスメーカーや工務店によっては土地探しも一緒にしてくれることがあるので、相談してみてください。参考:国土交通省 標準値・基準値検索システム(https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)
敷地(地盤)調査
・敷地状況の確認
・地盤調査
・法的規制の調査
・電気、ガス、水道施設敷地調査では、その土地にどのような注文住宅が建てられるかの現地調査を行います。
地盤調査結果によっては、地盤改良が必要になることがあります。・敷地やその周辺が埋め立て土地や盛り土で造成された土地
・過去に陥没があった土地、液状化や不同沈下の可能性がある土地など総合的な周辺情報により地盤の強化を要すると判断された場合は、地盤改良工事を実施します。
設計プランの提案・住宅ローン事前審査
・オリジナルプランのご提案
・仕様・設備・建築費などの打ち合わせ
・住宅ローン事前審査申し込み設計プランの提案では、ハウスメーカーや工務店のオリジナルプラン提案、仕様や設備・建築費を打ち合わせします。
設計プランでは、どのような注文住宅にしたいのか、しっかりとイメージを決めておくことが大切です。
「吹き抜けがほしい」「1階に和室を入れたい」など絶対に外せない条件は、優先順位をつけてメモしておきましょう。
また、家族の将来を見据えた間取りにすることも大切です。
老後生活でも使いやすい間取り、こどもが成長しても十分な収納など、一生モノの注文住宅だからこそ、生涯使える間取りを考えましょう。ご契約・住宅ローン本審査
・建築工事請負契約のご締結
・市や民間機関への建築確認申請
・注文住宅完成までのスケジュールのお渡し
・契約金、諸費用のご入金
・住宅ローン本審査申し込み設計プランが決まれば、工事請負契約をします。
また、このタイミングで住宅ローンの本審査申し込みをします。
工事請負契約を締結した後にプランを変更しようとすると、変更契約を結ばなければなりません。
変更契約には追加費用がかかる他、建築確認申請の後からでは変更できない項目もあるので、担当のハウスメーカーや工務店に確認しておきましょう。インテリアプランの打ち合わせ
・インテリアプランの打ち合わせ
・ご契約内容の確定インテリアプランを打ち合わせし、契約内容を確定させます。
設計プランで決めた間取りに加えて、家具の配置や窓の大きさなどの詳細を決めます。着工
・着工立ち会い
・着工金のご入金
・建物配置の確認立ち会い
・地鎮祭
・近隣挨拶
・打ち合わせで確定した内容で工事が始まります。着工前には、着工金の入金や地鎮祭、近隣挨拶を行いますが、「地鎮祭はしない」「近隣挨拶は現場監督に任せる」という方もいます。
着工したら工事の様子を見に行けるので、気になって毎日見に行くという方もいます。
ただし、様子を見に行くときは工事の邪魔にならないように注意してください。上棟
・上棟立ち合い
・上棟式
・中間金のご入金上棟とは、住宅の建築において、柱や梁など建物の基本構造が完成し、家の最上部で支える棟木(むなぎ)と呼ばれる木材を取り付けることを指します。
上棟式は、施主と工事を担当する大工さんや職人さん、工事関係者で行う式で、建物が無事に完成することを願うことを前提として、施主側と大工側の親睦を深めるためのきっかけとして行います。上棟式では塩やお神酒、米、おもてなしの料理や飲み物などを施主側が用意しますが、上棟式を行う行わないは、ハウスメーカーに一度確認をとってみましょう。竣工・検査
・竣工立ち会い
・引き渡しについて説明
・建物表示保存登記など各種書類手続き注文住宅が完成したら、完了検査の後に検査済証の発行を受けます。
また、竣工立ち会いの際には、完成した注文住宅に傷や汚れがないことを確認します。
竣工立ち会いで気になった部分で修正可能なところは、修正をお願いできるのでしっかりチェックしましょう。引き渡し
・最終金のご入金
・建物お引き渡し式
・各種設備取扱説明
・新居の鍵、保証書のお渡し最終金の入金、引き渡し式、各種設備取扱説明が終わったら、ついに引き渡しとなります。
ハウスメーカーや工務店の選び方
ここでは、自分にあったハウスメーカーや工務店の選び方について説明していきます。
品質の良さ
品質が良く、住みやすい注文住宅を建ててくれる建築会社を選びましょう。
建築事例を参考にしたり、モデルハウスを見学させてもらったりして確認するようにしましょう。提案力があるか
希望の条件を反映したプランを提案してくれる建築会社を選びましょう。
ただ希望の条件を汲み取ってくれるだけでなく、より使いやすいプランなどのさらなる提案をしてくれる建築会社は提案力があると言えます。予算内に収まるか
希望の条件を出して、できるだけ予算内に収めてくれる建築会社を選びましょう。
予算をオーバーしていたとしても、将来的に見ればコストをかけておいた方がメリットがある素材もあるので、予算オーバーしたからといって悪い建築会社だと決めつけないようにしましょう。担当者と合うか
担当者との相性も重要な要素です。
担当者の知識だけでなく、話が合うか、コミュニケーションが取りやすいかなど、スムーズに話が進まなければ理想の注文住宅が建てられません。注文住宅の支払い方法は?
ここでは、注文住宅の支払い方法について詳しく説明していきます。
3~4回に分割して支払う
一般的な注文住宅の場合、建築費用の支払いは3〜4回に分割して行います。
・工事請負契約時:建築費用の10%
・着工時(着工金):建築費用の30%
・上棟時(中間金):建築費用の30%
・引き渡し時:建築費用の残代金注文住宅を建てるときには、支払いのタイミングや計画についてしっかり説明してくれるハウスメーカーや工務店を選ぶようにしましょう。
住宅ローン審査の流れ
住宅ローンの審査は、「事前審査→本審査」という流れです。
計画段階で事前審査を受けておくことで、どのくらい借り入れできるかの目安が分かります。事前審査は、購入の申込をしていない検討中の土地で審査してもらうことも可能です。
事前審査が通り、建築工事請負契約を結んだ後に行うのが本審査です。事前審査とは異なり、より多くの情報をもとに審査が行われます。事前審査の内容に加えて物件の担保評価や物件瑕疵はないか、取引関係人に反社会的勢力はいないかなど、住宅ローン利用者から提出される各種書類をもとに審査が行われます。一般的に1週間から2週間程度審査に時間がかかります。つなぎ融資
つなぎ融資は住宅ローンを前借りする形で利用できるサービスで、住宅ローンの実行時期が引き渡し時の場合、それまでにかかる費用にあてることができます。つなぎ融資の期間は金利だけを支払い、注文住宅が完成すると同時に住宅ローンと一本化されます。
つなぎ融資は、住宅ローンと比べて金利が高く設定されているという特徴があります。
そのため、つなぎ融資は住宅ローンの融資実行時に一括返済しますが、つなぎ融資の完済までの期間は利息を支払う必要があり、期間が長ければ利息の負担が大きくなることを理解しておかなくてはなりません。なお、住宅ローンの実行時期が中間金支払い時という金融機関の場合には、つなぎ融資は不要になります。その他、土地の代金及び建物の代金をそれぞれ一つずつ住宅ローン契約することが出来る金融機関もあります。
※ハウスメーカーや金融機関によっては、つなぎ融資が利用できないことがあるので、事前に確認しておきましょう。
まとめ
今回は注文住宅のご相談から引き渡しまでの流れを紹介しました。
注文住宅の引き渡しまでをスムーズに進めるためにも、全体の流れをイメージしておくことが大切です。
今回紹介した流れや支払い方法を参考にして、納得のいく注文住宅を建てられれば幸いです。 -
ライフ・パートナーズ Vol.60
- 投稿日


-
注文住宅 予算オーバーにならないために
- 投稿日

こんにちは!名稲建設株式会社です!
注文住宅を建てるときに陥りがちなのが、想定していた予算よりも費用がオーバーしてしまうことです。
高性能なキッチンなどの設備、おしゃれで高級な床材や建具、子どもたちが遊べる庭など希望の条件をどんどん入れていくと、予算オーバーになるのはよくあることです。
今回は、注文住宅で予算オーバーにならないために気を付けることについて解説していきます。「理想の注文住宅を建てたいけど、予算オーバーを防ぎたい」
という方は必見の内容になっているので、ぜひご一読ください。
注文住宅で予算オーバーになる原因とは
・設備や構造にこだわりが多すぎる
・補助金制度を利用していない
・諸費用・付帯工事を考慮していない注文住宅で予算オーバーになる原因には、上記3つが挙げられます。
設備や構造にこだわりが多すぎる
設備や構造にこだわりすぎると、予算オーバーになりがちです。
ウッドデッキ、特徴的な屋根や家の形、ダウンライト、高性能なキッチンなど注文住宅はこだわろうと思えばいくらでもこだわれます。
そこで、自分たちの要望をすべて通そうとすると、必然的に予算オーバーしてしまいます。補助金制度を利用していない
・こどもみらい住宅支援事業
・地域型グリーン化事業
・自治体からの補助金注文住宅を建てるときに利用できる補助金制度はいくつもあります。
例えば、「こどもみらい住宅支援事業」は、子育て支援を目的とした住宅補助金制度です。
子育て世帯や若者夫婦世帯を対象としており、省エネ性能の高い住宅を新築するか、省エネ性能の高い住宅にリフォームすることで、補助金を受給できます。「こどもみらい住宅支援事業」について、もっと詳しく知りたいという方はこちらをご覧ください!
「こどもみらい住宅支援事業」について解説します!–名稲建設株式会社(https://meito-fuso.com/column/kodomomirai/)
補助金を受給できれば、注文住宅のグレードをワンランクアップさせることも可能ですので、受給可能な補助金制度を調べて、検討してみることをおすすめします。
諸経費・付帯工事を考慮していない
工事分類
内容
総予算に対する割合
本体工事費用
基礎・構造・設備工事
75~80%
付帯工事費用
ガス・給排水・外構工事
15~20%
諸経費
申請費用・税金
5~7%
注文住宅の費用や相場 大工が教える失敗しない家づくり(https://ie-daiku.org/souhiyou.html)
注文住宅に限らず、住宅を購入する際には本体工事費用と別に、付帯工事費用、諸経費がかかります。
それぞれ費用の相場は上記のようになっています。
注文住宅を建てるために当てられる本体工事費用は、総予算の75~80%となっているので、予算全てを注文住宅に当てられると考えてはいけません。注文住宅の予算を削る方法6選
この項目では、注文住宅の予算を削る方法6選をご紹介します。
延床面積をできるだけ小さくする
注文住宅は一般的に「床面積×坪単価」で建築費用が計算されます。
坪単価とは家を建てるときの1坪(タタミ2枚分/およそ3.3㎡)あたりの建築費のことです。坪単価が50万円の住宅メーカーの場合、床面積40坪の注文住宅を建てるなら
40坪×50万円=2,000万円床面積を減らし35坪の注文住宅を建てるなら
35坪×50万円=1,750万円
になります。床面積を5坪(約16.5㎡)減らすだけで、250万円のコストダウンです。
自分たちの生活スタイルにあったちょうどいい広さなのか、もう1度検討することをおすすめします。間取りを見直す
・部屋・窓の数を減らす
・和室を作らない
・間仕切りを減らす
・バルコニーを必要以上に大きくしない
・部屋を本当に必要な広さにする
・収納スペースをまとめる間取りだけで、これだけの見直しポイントがあります。
こども部屋の間仕切り壁をなくしたり収納スペースをまとめたりと、必要のない余計な空間を作らない、まとめられるものはまとめることが予算オーバーを抑えるコツです。水回りの設備は1カ所・1つの階にまとめる
トイレ、キッチン、お風呂など水回りの設備は、1カ所、1つの階にまとめるようにしましょう。
1つの階にまとめることで配管が長くならず、前述した付帯工事費を抑えられます。
トイレを1階にも2階にも設置したい場合は、2階のトイレを1階の真上にすると、配管の長さを節約できます。建材や設備のグレードを落とす
注文住宅を建てるとき、最新式のキッチン、太陽光発電パネルや無垢材など、高機能高品質な設備や素材のカタログを見ているとワクワクしますよね。
ですが、注文住宅では、素材や設備のグレードを上げすぎてしまい予算オーバーになることが多いです。
システムキッチンでは、建築会社標準仕様のキッチンを選択すれば追加費用はかかりませんが、グレードを上げるとなるとオプションでの対応になることが多いので、高いもので200万円以上の追加費用がかかります。
キッチンのこだわりを捨てて、標準仕様のものにすれば、約200万円のコストダウンになることがわかります。
高級なシステムキッチンなど、グレードの高い設備が本当に必要なのかをよく考えると、予算オーバーを防ぐことに繋がります。予算オーバーしないで後悔のない注文住宅を建てるためには
・こだわりの優先順位をつける
・予算はオーバーするものと考えるこの項目では、予算オーバーしないで後悔のない注文住宅を建てるために必要な上記2つのポイントについて、解説していきます。
こだわりの優先順位をつける
注文住宅の予算オーバーを防ぐためには、よほどの予算がない限り、希望条件のどれかを削らなければなりません。
・全体から決め、細部は後回しにする
・設備の使用頻度は高いのか
・将来的に不便にならないか上記のようなルール決めをしておくことで、優先順位をつけやすくなります。
注文住宅の細部は後からでも変更できることが多いため、予算オーバーになったときにも調整が可能です。注文住宅のプランは全体から決めていきましょう。
また、希望の設備の使用頻度は高いのかをよく考え、その設備が本当に必要なのか十分に吟味する必要があります。
出産や老後のことを考えて、注文住宅を建てることも重要です。
3階建ての注文住宅や、勾配のきつい階段にしてしまったせいで老後に不便になってしまった、ということにはなりたくありませんよね。
注文住宅で予算オーバーしたときは、将来のことを考えたときに削れるポイントがないのかを考えてみてください。予算はオーバーするものと考える
そもそも、注文住宅の予算はオーバーするものと考えるようにしましょう。
理想の注文住宅を建てようと思うと、追加の設備や間取りによって費用はどんどんかさんでいきます。
そのため、2000万円の予算にするなら2200万円用意するなど、予算の+10%を用意しておくことで予算オーバーに余裕を持って対処できます。まとめ
今回は、注文住宅で予算オーバーにならないためのポイントを紹介してきました。
1生に1度の機会かもしれない注文住宅に、理想を詰め込みたいという気持ちはわかります。
優先順位のルール決めをしっかり行い、後悔のない注文住宅を建てられるようにしましょう。
名稲建設株式会社では、予算内で最善の提案ができるように努めています。一緒に理想のマイホームを検討しましょう。 -
土地探しで起こりやすい後悔や失敗した事例など土地探しのポイントをご紹介します!
- 投稿日

こんにちは!名稲建設株式会社です!
土地の購入は人生 の中でも大きな買い物であり、注文住宅等の購入と同時に検討することが多く、もちろん後悔・失敗などのリスクは負いたくないものです。
岐阜県岐阜市を例にとると、2022年2月現在購入可能な土地は約300件とかなりの数です。
これだけ多いと、土地探しに迷ってしまうのはしょうがないですよね「一生に一度あるかないかの土地探しで失敗したくない」
「土地探しで失敗しないためのコツを知りたい」今回は、この様な悩みをお持ちの方に向けて、土地探しの失敗事例を押さえ、後悔・失敗しないためのコツを解説します。
参考:SUUMO 東海版(https://suumo.jp/tochi/gifu/city/)
土地探しで後悔・失敗した事例をご紹介
慎重になるべき土地探しですが、購入した後に後悔している方は少なくありません。
ここでは、土地探しの後悔した事例・失敗した事例を紹介します。予算オーバー
土地探しでは、土地の価格だけに注目しがちですが、その他にも諸経費がかかります。
諸経費というと、不動産取得税や仲介手数料などの経費になるのですが、諸経費を予算に含めなかったことで、失敗する事例は数多くあります。・「不動産の価格(課税標準額)」×「税率(3%)」=「税額」
上記は、岐阜県の不動産取得税計算方法です。
例えば1,000万円の土地を購入した場合、30万円も不動産取得税がかかります。※ただし、宅地及び宅地比準土地(市街化区域農地や雑種地等)を取得した場合の不動産取得税の課税標準額については、次のような特別措置があります。
取得時期
課税標準額
~令和6年3月31日
固定資産課税台帳登録価格の2分の1
出典:不動産取得税しおり 岐阜県(https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/247728.pdf)
周辺環境の悪さ
周辺環境の悪さは、住み始めてからわかることが多い、土地探しで見落としがちな要素です。
「土地を購入して住んでみたら、日当たりが最悪だった。」
「周りに田んぼが多く、湿度が異常に高かった。」見つけた土地が希望の条件全てをクリアしていたとしても、一目ではわからないマイナスポイントがあるケースがあるので、注意してください。
利便性の悪さ
通勤通学、買い物の利便性などは、把握しているつもりでも、実際は許容できないレベルだったということがあります。
休日に土地探しをしていたため、休日の交通量で駅までの時間を計算していたら、朝と夕方のピーク時には、計算の倍以上の時間がかかったというケースです。
その他にも、土地を購入して何十年後に足腰が悪くなってしまい、駅に行くまでにある坂を登ることが億劫になり、駅までいけなくなったというケースもあります。ご近所トラブル
ご近所トラブルは、土地探しの段階ではなかなか気づけません。
住んでみてから初めて、異臭やペットの鳴き声が問題として出てきたり、家を建てているときに工事の音でトラブルになったりと、理由はさまざまです。法規制・土地が特殊
・用途地域の建ぺい率、容積率の制限で、建てたい大きさの家が建てられない
・旗竿地(細い路地の先にある土地)になっていて、建築コストがかかる法規制や土地の特殊な形状のせいで、上記のような失敗をすることがあります。
後悔しないためにも、「どんな用途地域なのか」「土地の形状によるデメリットはないか」に注意する必要があります。他の人に先を越された
希望の条件にあった土地を見つけ購入を検討していたが、悩んでいるうちに他の人に買われてしまったということがあります。
希望の条件にあった土地というのは、他の人の希望条件にも当てはまることが多いので、先に購入されてしまうというケースが多くあります。
再度、条件にあった土地を探そうとしてもなかなか見つからず、振り出しに戻ってしまいます。土地探しで後悔・失敗した人の共通点
前述した土地探しの失敗事例をふまえて、土地探しで後悔・失敗した人の共通点を紹介します。
建築費用などを含めトータル的な目線で土地探しをしていない
・家を建てるつもりなのに不動産会社だけに相談している
・土地代と建築費用だけを計算している土地探しで失敗する人は、土地と建築費用以外の予算や土地購入後の施工についてあまり考えていません。
建築を踏まえた土地選び、土地代や建築費用の他にも諸費用を入れた総予算を計算するようにしましょう。リサーチが足りていない
土地探しで失敗する人は、リサーチが足りておらず、周辺環境の悪さ、利便性の悪さに気づけていません。
購入予定の土地がどのような土地なのか、どんな条例や法律が適用されるのかを詳しく調べたり、近隣住民に挨拶するついでに話を聞いたりすることが重要です。一定の時刻・季節しか確認していない
土地探しで失敗する人は、購入予定の土地を一定の時刻・季節にしか確認していません。
少なくとも、朝昼晩の3つの時間帯それぞれの様子を確認するべきです。
そうすることで、「早朝から隣家の生活音がうるさい」「バイクの音が毎晩鳴り響いている」といった、住み始めてからでしか気付きづらいことにも先に気付けるかもしれません。土地探しで後悔・失敗しないためのポイント・コツとは
ここでは、土地探しで後悔・失敗しないためのポイントやコツを紹介します。
これから土地探しをする人、土地探しをしている最中の人は、ぜひ参考にしてください。ハウスメーカー・工務店にも同時進行で相談する
土地探しの際は、ハウスメーカー・工務店にも同時進行で相談することがコツです。
土地探しでは、希望条件の土地を見つけることに注力しがちですが、それでは建築の段階で予算面の失敗をしてしまいます。
土地購入から注文住宅までの総予算を計算しているつもりでも、注文住宅のプランを練っていると予算オーバーになることはよくあります。
予算オーバーを防ぐためにも、土地探しと同時進行でハウスメーカー・工務店に相談し注文住宅のプランを練りましょう。
「希望の土地を購入するために、注文住宅の設備を諦める」「希望の注文住宅を建てるために、土地の条件を下げる」といった選択ができるようになります。法律を満たしているかを確認
・用途地域
・接道義務
・容積率、建ぺい率、高さ制限
・防火地域、準防火地域 など希望の注文住宅を建てるために、土地が法律を満たしているか確認することも土地探しのコツです。
上記の項目によって、建物の形状、建材の費用が変わってくるので、予算オーバーを防ぐためにも必須の確認項目です。出典:国土交通省 建築関係法の概要(https://www.mlit.go.jp/common/000134703.pdf)
時間・時期を変えて下見に行く
・休日だけでなく、平日にも下見に行く
・晴れの日以外にも曇りの日など、さまざまな天候の状況を確認する
・特定の時間だけでなく、朝や夜などの時間帯の下見に行く上記を意識するだけで、購入予定の土地のいろいろな顔が見られます。
休日か平日か、昼か夜かによって、周囲の騒音問題が見えてくることもあります。優先順位を決める
1.土地の面積
2.会社までの距離
3.地盤の強さ
4.周辺環境土地に求める要素の優先順位は、必ず決めましょう。
上記のように優先順位を決めることで、土地探しで妥協できる点、これだけは外せない点が浮き彫りになり、土地探しがスムーズに進むことは間違いありません。過去どのように利用された土地か調べる
・元々が田んぼだった
・過去に地盤沈下、液状化現象があったこのような土地は、地盤沈下、地震で建物が倒壊する可能性があります。
ですが、しっかりと地盤改良をしている土地を購入すれば問題はありません。
過去の土地利用を調べて、不動産会社に地盤の状況を確認してみてください。予算に影響する?土地探しの注意点
土地によっては、普通以上に費用がかかる土地があります
ここでは、追加費用がかかる土地、かからない土地の違いを説明します。追加費用がかかる
・水道やガスなどのインフラが引き込まれていない
・道路と高低差がある
・元々が沼地だった
・古家が建っているこれらに当てはまる土地は、追加費用がかかります。
追加費用がかかりますが、デメリットを交渉要素にできる場合があるので、不動産会社に交渉してみることをおすすめします。追加費用がかからない
・水道やガスなどのインフラが整っている
・道路と高低差がない
・強固な地盤であるつまりは、「追加費用がかかる」の項目で紹介した要素と逆の土地であれば、基本的に追加費用はかかりません。
できるだけ追加費用のかからない土地を選ぶことで、スムーズに土地利用へ進めます。まとめ
今回は、土地探しの失敗事例を踏まえて、土地探しのポイント・コツを紹介しました。
住宅取得における土地購入は、自分が暮らしていく街・場所を決めるということです。長期的、あるいは一生住む場所になるので、後悔しないように過去の失敗事例を参考にしましょう。
土地探しからのご相談も承っています。気軽にお問い合わせください。 -
ライフ・パートナーズ Vol.59
- 投稿日


-
意外に多い「住宅ローンの失敗例」をご紹介!
- 投稿日

こんにちは!名稲建設株式会社です!
注文住宅などの住宅を購入するときには、住宅ローンを組むのが一般的ですが、「住宅ローンを組んで失敗するのが不安」
「住宅ローンの失敗したくない」という不安を持つ方は多いのではないでしょうか。
今回は、住宅ローンの失敗事例、住宅ローンで失敗しないための方法について紹介します。
この記事を読むことで、住宅ローンで失敗しないためのポイントがわかるので、絶対に失敗したくないという方はぜひ参考にしてください。住宅ローンの失敗事例を紹介
まずは、住宅ローンの失敗事例を紹介します。
よくある失敗をピックアップしたので、参考になる点が多いと思います。頭金が少なすぎた・多すぎた
住宅を購入するときには、自己資金から頭金を捻出するのが一般的です。
「頭金が少なすぎた」のケースは、希望の物件の価格が想定よりも高く、頭金をあまり出せなかったため、月々の支払いが多くなった、借り入れ年数が増えてしまったというパターンです。
「頭金が少なすぎた」のケースには、頭金0円で住宅ローンを組んだというパターンもあります。住宅ローンは頭金0円で組むことも可能ですが、借入金額がより大きくなるため月々の返済額も大きくなります。返済で生活が苦しくなるようなことは絶対に避けましょう。
「頭金が多すぎた」のケースは、頭金を払いすぎたあまりに自由に使えるお金がなくなった、生活資金や子供の教育資金に十分なお金が確保できないというパターンに陥る傾向があります。ボーナス返済に頼りすぎた
住宅ローンはボーナス返済を利用することで、月々の返済額が減らせます。
しかし、ボーナス返済に頼りすぎるとリスクがあります。「コロナ禍でボーナスがかなり減ってしまった」
「転職したら、その会社にはボーナスがなかった」ということが起きる可能性は十分にあります。
社会情勢や経営状況によって金額が変わるボーナスに頼りすぎることは、あまりおすすめできません。繰り上げ返済しすぎた
住宅ローンには、ローンを前倒しで返済できる「繰り上げ返済」という制度があります。
繰り上げ返済すると、返済期間を短くしたり、月々の返済負担を少なくしたり、というメリットがあります。
しかし、繰り上げ返済をしすぎたばかりに、資金が少なくなり生活が苦しくなってしまったというパターンがあります。
病気にかかったり、転職をしたりと、人生の転機には収入が不安定になることがほとんどです。
収入が不安定になることを見越して、ある程度の資金を手元に残しておくことが大切です。借り換えで失敗した
「審査に通らなかった」
「安易に借り換え先を決めてしまい、後からよりお得な銀行を見つけた」
「審査が長引いてしまい、その間に金利が変わった」借り換えによって住宅ローンの金利が低くなったという成功例はよく聞きますが、借り換えで上記のような失敗をすることもあります。
金利タイプを安易に選んだ
金利が上がって生活が苦しくなってしまった、というケースです。
住宅ローンには、「変動金利」と「固定金利」の2つの金利があります。
変動金利は市中金利の動向によって、返済期間中の金利が変動するタイプ。
対する固定金利は、借り入れ開始時に完済までの金利が固定されるタイプで、「全期間固定型」と「固定期間選択型」に分けられます。「全期間固定型」は、借り入れ時に確定した金利を返済終了まで払い続けるローンで、世の中の金利水準が上下しても影響を受けることはなく、返済終了まで金利は変わりません。
「固定期間選択型」は、一定期間の金利が固定されるローンです。契約時に借り手が3年、5年、10年、15年などの固定金利期間を選択します。全期間固定型と比べて金利が低く、選ぶ期間が短いほど金利が下がるのが一般的で、期間内は金利が変わりません。固定期間終了後は自動的に「変動金利型」に切り替わりますが、再び固定期間を選択することも可能です。近年は今までにないほど低金利といわれています。今後もこの状態が長く続くと考えられていることから固定金利より金利が安く設定される変動金利の方が人気です。
2021年4月の「住宅ローン利用者の実態調査」によると、注文住宅を購入した人(敷地同時取得)の中で、変動金利を選んだのは68.9%。固定金利を選んだのは21.6%。全期間固定型を選んだのは9.5%と、変動金利が大半を占めています。
しかし、金利が上昇したときのリスクは無視できません。
金利が上がれば返済額が増えて、家計を圧迫することになるので注意が必要です。参考:住宅ローン利用者の実態調査(https://www.jhf.go.jp/about/research/loan_user.html#data01)
諸経費を考えていなかった
・固定資産税
・不動産取得税
・手付金
・印紙税注文住宅などの住宅を建てるためには、住宅そのものの費用の他にも、上記のような税金やメンテナンス費用などの諸経費もかかります。
そのため、払う必要があるものが住宅ローンだけだと考えていると、諸経費を払う余裕がなくなります。
新築一戸建て注文住宅は工事費の3~6%(土地がある場合)、建売住宅は物件価格の6~9%が相場ですので、予算に組み込んでおきましょう。参考:ライフルホームズ 新築一戸建ての諸経費シミュレーション(https://www.homes.co.jp/cont/money/money_00441/)
団体信用生命保険に加入しなかった
団体信用生命保険(団信)に加入しておくことで、死亡したり高度障害状態になった際に、保険金で住宅ローンを完済できます。
一般的には団信の加入は必須条件ですが、フラット35では団信の加入は任意になります。
団信に加入していないと、残された家族がローンを返済することになるので、リスクに備える住宅ローンで失敗した人の共通点
これまでに紹介した住宅ローンの失敗事例を踏まえて、住宅ローンで失敗する人の共通点を解説します。
情報収集が足りていない
住宅ローンを組むなら、住宅ローンに関する情報収集は欠かせません。
住宅ローンをどの金融機関で借りるべきなのか、地方自治体で利用できる補助金制度はないのか、などを必ず調べるようにしましょう。
また、諸経費、金利タイプについてなど、住宅ローンを考える上で知っておくべき情報はいくつもあります。
あとになってから困らないように、情報を事前に集めておきましょう。返済計画・貯蓄計画をしっかり立てていない
返済計画と貯蓄計画をしっかり立てないと、返済がうまく行かず失敗する可能性が高くなります。
家族の病気、転職、ボーナス減額などのリスクを踏まえて、余裕をもった返済計画にすることで、不安の少ない住宅ローンにできます。
また、住宅ローンは長期間にわたるローンなので、長期的な視点で計画することが大切です。住宅ローンを組む金融機関、金利タイプをよく考えて決めることはもちろんですが、まずは無理のない範囲で借入金額を決めましょう。すべて営業マン任せにしてしまった
「すべて営業マン任せにして失敗…」というのはよくある失敗パターンです。
中には親身になって住宅ローンを提案してくれる営業マンもいますが、年収に対して限度額まで借りさせようとする営業マンもいます。
営業マンからの提案を鵜呑みにするのではなく、自分で金融機関に問い合わせたり、シミュレーションをしてみたり、営業マンの提案内容が妥当かどうかしっかりと自分で確認する必要があります。住宅ローンで失敗しないためには
ここでは、住宅ローンで失敗しないための方法について解説していきます。
これから住宅ローンを組むという方は、ぜひ参考にしてください。額面ではなく手取りでシミュレーションする
住宅ローンをシミュレーションする際は、額面ではなく手取りでシミュレーションしてください。
額面ではなく手取り収入で考えることによって、余裕のある返済計画が立てられます。
額面で住宅ローンを組んで、あとから修正することは難しいので注意が必要です。将来の生活変化を想定する
住宅ローンを組むときは、将来の生活変化を想定してください。
例えば、夫婦で物件を購入する場合、将来子どもができたら教育資金が必要になります。
自分の親が高齢になり要介護になったときには、介護費用が必要になります。
将来増えるだろう出費を踏まえて、月々の返済額を決めることで、生活が変化しても焦ることなく住宅ローンの返済ができます。住宅ローンに詳しくなる
住宅ローンに詳しくなることで、住宅ローンに不安を感じることは少なくなります。
前述したとおり、営業マン任せにしてしまうなど、住宅ローンについて自分で考えないと失敗してしまうケースが多いです。・金利タイプの違い
・各金融機関の違い
・返済方法の違い上記のように専門家に任せたくなるような内容でも、自分の知識で検討すれば失敗することは格段に少なくなります。
最後にどうするか決められるのは購入者です。
失敗しないためにも、専門家の意見を参考にしつつ、自分の意志で住宅ローンを選びましょう。まとめ
今回は住宅ローンの失敗例について、ご紹介しました。
住宅ローンの失敗は、どれも知識不足によって起きてしまいます。
住宅ローンは長期の返済になるため、知識を補い、将来を見据えた長期的な目線で考えるようにしましょう。
名稲建設株式会社では、お客様目線で最善の住宅ローンを提案させていただいております。検討段階でも結構ですので、まずは気軽にお問い合わせください。 -
ライフ・パートナーズ Vol.58
- 投稿日
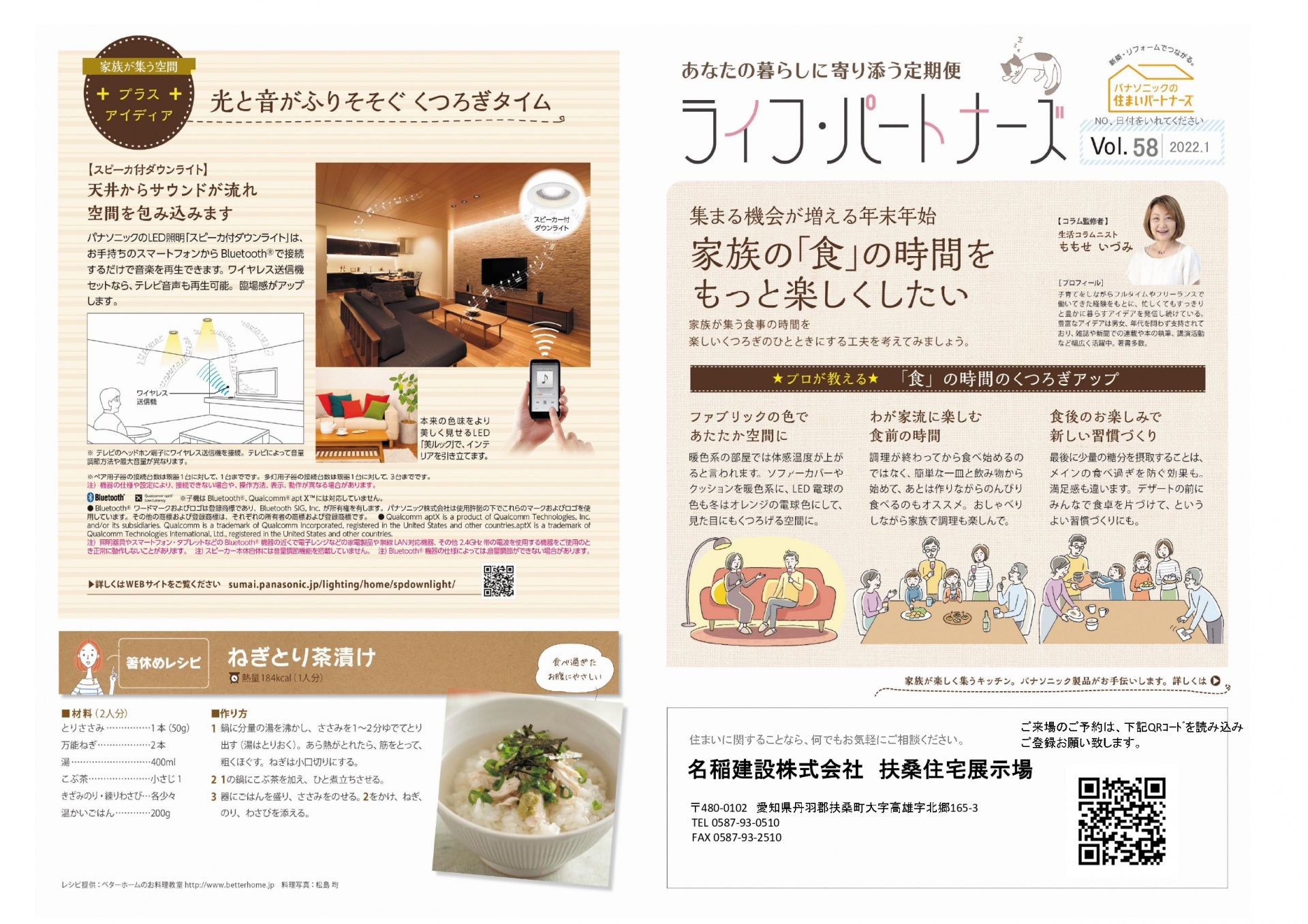

-
住宅ローン減税はどう変わるのか
- 投稿日

こんにちは!名稲建設株式会社扶桑展示場です!
2021年の年末に期限を迎える「住宅ローン減税」ですが、政府は4年間延長し控除の在り方を見直した上で、改正することを決めています。12月10日には方針が固まっているので、実際に2022年度住宅ローン減税がどう変わっていくのか?について詳しくお伝えしていきます。2021年の住宅ローン控除の振り返り
住宅ローン減税とは、その名前の通り住宅ローンを利用して住宅を購入した人のためにある減税制度になります。
2021年の住宅ローン減税は、原則10年間、年末の住宅ローン残高の最大1%が所得税や住民税から控除されています。(所得税から控除しきれない金額がある場合には、住民税の一部からも控除される)
控除額は10年間で最大400万円、長期優良住宅などの環境に配慮された住宅に関しては最大500万円です。
原則10年ですが、一定の要件を満たした場合、最長13年まで延長ができます。
理由としては、新型コロナウイルスにより住宅需要の低下が懸念されたためです。
延長できる要件は、以下のようになっています。・契約期日が2021年9月末までの注文住宅
・契約期日が2021年11月末までの分譲、中古住宅
・入居期日が2022年12月末本来であれば、すでに契約期日に関しては過ぎているので延長は無理?と思うかもしれませんが、2022年に住宅ローン減税が改正されることで新築住宅などの消費税課税住宅に限っては、2025年度まで控除期間を13年に延長できます。
2022年度税制改正大網はどうなる?
税制改正大網というのは税制改正の大元となる内容を意味しています。
今回、どんな点が2021年と変わっていくのか、以下で説明していきます。①控除率が1%→0.7%に変更
以前は支払う利息よりも多く控除を受けることができる「逆ざや現象」が起きていました。
こうした現象を是正するためにも、1%を0.7%に縮小することが決まっています。控除率に関しては2025年末まで据え置かれることが決定しています。②控除期間は13年に延長はそのまま
2021年から控除期間は原則10年、要件を満たした場合は13年まで控除期間が延長できます。
この部分は、2022年も変更はなくそのままです。今現在も、新型コロナウイルスの影響によって経済的な影響が続いていることが理由といえます。ただし、控除期間延長の対象は新築住宅および不動産業者が再販している消費税課税住宅だけです。つまり、一般の売り主が売っている中古住宅に関しては、今までと変わらず10年の控除期間となります。③減税の対象となる借入残高の上限の縮小
2021年の時点では、長期優良住宅などを除いた一般住宅の最大控除額は減税の対象となる借入残高の上限が4,000万円で控除率が1%のため年間40万円でした。2022年には、減税の対象となる借入残高の上限が3,000万円に引き下がり、控除率が0.7%のため最大控除額は年間21万円となります。2021年の控除額からすると半減といってもいいくらいに縮小されています。減税の対象となる借入残高の上限は2023年まで3,000万円、2024年、2025年は2,000万円とさらに減ります。
この部分だけ見ると非常に改悪、と感じられますがあくまで「省エネ基準に適合していない一般住宅だけ」となります。長期優良住宅や今話題のZEH住宅(Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略)などは別途、減税の対象となる借入残高の上限や控除期間で上乗せ措置がされるので、混乱しないようにしましょう。以下のように入居時期によって減税の対象となる借入残高の上限は違ってきます。
※ZEH住宅:エネルギーを作り出す家のことを指していて、他からのエネルギーを極力必要としない住宅のことを指しています。
・2022年、2023年に入居した場合
認定住宅は減税の対象となる借入残高の上限が5,000万円、ZEH水準の省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円です。
・2024年、2025年に入居した場合
認定住宅は減税の対象となる借入残高の上限が4,500万円、ZEH水準の省エネ住宅は3,500万円、省エネ基準適合住宅は3,000万円です。
控除率0.7%、控除期間13年は一律となっています。④所得制限
所得制限は以前から設けられていましたが、2021年の場合は3,000万円以下ですが2022年には2,000万円以下に引き下がります。さらに、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅に住んでいる場合は1,000万円以下とそれぞれ所得制限が設けられています。
⑤中古住宅の要件が緩和
2021年までは、住宅ローン控除を受けるためには木造であれば20年、耐火構造であれば25年といった築年数を下回る中古住宅しか適用がありませんでした。2022年の改正によって、1982年以降に建築された住宅は新耐震基準適合住宅とみなし、証明書類などもなしで対象になります。
すでに住宅ローンを組んでいる人はどうなるの?
2022年に改正される住宅ローン減税ですが、今現在すでに住宅ローンを組んでいる人にも適用されるのか?と不安に感じている人も多いです。通常でいえば、改正案が適用されるのはあくまで改正案がスタートした後に住宅ローンを組んでいる人が対象になります。以前から何度も住宅ローン減税は改正されてきましたが、すでに住宅ローンを組んでいる人達に対して改正内容を適用することはありませんでした。通常から考えても制度が変わったとして現在利用している人も全て変える、というのは考えにくいことです。そのため、2021年に住宅ローンを組んで、控除率1%が適用されたのであれば2022年以降制度が変わったとしても、変わらずに利用ができるので、安心しましょう。
まとめ
2021年12月に入り、調整が進められていることから今後住宅を購入する人達は動向に注目していたであろう住宅ローン減税は2022年で見直される部分、据え置かれる部分とそれぞれあります。
2022年度の税制改正の内容が実際に適用となるのは原則的に2022年4月1日からです。業者とこうした制度改正を見越したスケジュール調整を行うことがとっても大切になります。自身の負担を軽減させるためにも、しっかりと住宅ローン減税については今後も動向を注視してきましょう。 -
住宅ローン選びのポイントをご紹介します!
- 投稿日

こんにちは!名稲建設株式会社扶桑展示場です!
住宅を購入する際、悩むのは住宅ローンをどこで組むかということです。
金融機関はどうしたらいいのか、大手のほうが良いのか?など、いろいろ疑問がありますが、大事なのは金融機関のネームバリューではありません。
今回は、住宅ローン選びのポイントをお伝えしていくので、比較検討の参考にしてみてください。住宅ローンを借りる前に確認しておきたいこと
住宅ローンを選ぶ前にまず確認しておくことは、どこにどんな家を購入して、どんな設備にするのかという点です。住宅を注文してから住宅ローンを決める人は多いですが、そもそも購入する家にはどの程度の金額をかけられるのかを考えておく必要があります。
一般的に、住宅ローンを組む際に自己資金は物件価格の20%以上が理想とされているので、自己資金として出せる金額から逆算していくと住宅購入の予算を立てられます。
住みたい場所や広さによって、金額は変わってくるので業者と相談しながら予算を決めても問題はありません。また、最近では「頭金0円」でOKな金融機関も増えてきているので、自己資金をどうしていくかはまず考えた方がよいです。
頭金が必要な場合は、最初は大変ですが借入金額が少なくて済むので、先々の支払いが楽になります。一方で、頭金0円の場合は借入金額が多くなりますが、購入当初は自己資金を貯めておける利点もあります。
どちらが正解というわけではないので、自身の資金計画に合わせて決めるようにしましょう。借り入れ可能金額のチェックも重要
頭金0円にして、自己資金を残しておきたいと思っていても、実際に借り入れが可能なのかは審査によります。絶対という保証はないので、事前に自分の収入であればどの程度借り入れが可能なのかチェックしておくと良いです。
各金融機関のサイトでは借り入れのシミュレーションができるので、年収と借り入れ希望期間を入力してチェックしておきましょう。住宅ローン選びのポイント
住宅ローンを選ぶ際、金融機関によって良い悪いが決まると思う人もいますが、実際は選ぶ際のポイントがあります。金融機関が大きいかどうか、メガバンクなのか地銀なのかが重要なのではなく、住宅ローンの内容が大事です。
金利タイプ
住宅ローンを比較検討する際に、もっとも大事なことは「金利」です。金利と一言で言っても、以下のようにタイプが分けられます。
全期間固定金利
言葉の通り、借り入れした際の金利が返済スタートから終了まで一定しているタイプです。将来的に市場金利が上昇しても影響を受けず支払い計画が立てやすい反面、高めの金利に設定されていることが多いので、金利が下がった時の恩恵を受けられないのはデメリットです。
変動金利
市場金利によって支払う金利が変動するタイプです。借り入れスタート時よりも金利が下がっていた場合、毎月の返済額が減りますが、市場金利によって左右されるので上昇すればそれだけ毎月の返済額も増えて支払い計画が立てにくいのはデメリットです。
固定金利期間選択
借り入れスタート時から一定期間は適用金利が固定されていて、期間が終わったのち自身で金利のタイプを選択できるタイプです。最初の金利タイプを固定金利にした後、変動金利にすることも可能です。返済計画を立てやすいことはメリットですが、固定金利の間は金利が高くなりがちです。
金利が何%かは、それぞれの金融機関によって違いがあるため、少しでも金利を低くできるように比較検討し、自身のライフプランや考え方によって決めるようにしてください。返済方法
住宅ローンの返済方法は、単純に決められた額を払えばOKというわけではありません。金利がある以上、利息の返済も必要になるので、元金と利息それぞれどれくらいに当てられるのかはとても重要なポイントです。
返済方法は、2つに分けられます。元利均等返済
完済まで金利の変動がなければ、返済額が一定額となる返済方法です。
元金均等返済
毎月の返済額に占める元金を均等にして、残った元金に対して利息額を上乗せしていく返済方法です。
多くの場合はどちらか選択することができますが、金融機関によっては元金均等返済は選べないという可能性もあるのでしっかり確認しましょう。
諸費用
家を建てる際、単純に建築費用だけ必要になるわけではありません。そのほかにも、事務手数料、印紙税、登記費用など思わぬ諸費用が加算されることが多いです。さらに、住宅ローンを組む際の手数料や保証料なども加算されるので、諸経費だけで数十万必要なんてこともあり得ます。
登記費用などは金融機関で違うということはありませんが、異なってくるのは保証料です。金融機関によって借入金額の何%かかるのかは違いが出てくるので、借りる前にしっかりと確認してしておいてください。金利タイプの変更手数料、繰上げ返済手数料なども金融機関で違うので、注意しましょう団体信用生命保険の保障内容
住宅ローンを組む際、多くの場合は団体信用生命保険(団信)への加入が必須になります。住宅ローンの契約者に万が一のことがあった際に、ローンの残債を保険金で完済させるというものになります。金融機関によっては、万が一の際以外にも「三大疾病・八大疾病・ガン保障」など、特約を設けている場合もあるので、自身が希望する内容の保障か確認が必要です。
自分に最適な住宅ローンを組む考え方
住宅ローンを組む際の考え方としては、どんな金融機関に依頼するのが良いのかではなく、自分のライフプランや希望通りの借入金額を借りられるのか?という部分です。金利や返済方法だけではなくて、団信の保障内容や諸費用によっても細々と違いはあります。返済計画やどれくらいの金額なら毎月確実に支払いができるのかなど、しっかり最初の段階で考えておくことがとても重要になるので、よく検討するようにしてください。
また、金融機関の選び方だけではなくてその審査にしっかりと自身が通るのかについても検討しなくてはいけません。事前シミュレーションを行って、住宅ローンの選択肢の幅を広げてください。できる限り自己資金を用意しておいた方が自由度の高い住宅ローンを組むことができますが、その点も購入時の自分の状況を把握してから決めます。最終的に困ったらまずは相談
どれだけ検討したとしても「どこに借りたらいいんだろうか…」と思う場合は、銀行やハウスメーカーなどに相談すると良いです。住宅を購入する際に、当然業者に相談することになるので合わせて住宅ローンについても相談してみましょう。業者によっては、資金計画についてもしっかりと相談に乗ってくれるところも多いので、迷った際は専門家の意見を聞くことが大事です。
また、借り入れをするか決めかねている場合は悩んでいる金融機関それぞれに直接相談してみるのも1つの手といえます。最近では対面での相談以外にも電話やオンライン上で気軽に相談することが可能です。
具体的にどういう部分で悩んでいるか、基本的な質問や手続き方法、注意点などをよく相談してみてください。金融機関の相談員は住宅ローンを専門に受け持っているので、なんでも相談に乗ってもらうことができます。金融機関によっては平日だけではなく、休日も対応可能なところもあるので、迷ったら悩まず相談することが大事です。まとめ
住宅ローン選びでは、金利や借入金額の支払方法などいろいろ検討しなくてはいけない部分があります。金融機関によって特色も変わってくるので、自分の希望やライフプランを考慮しながら、納得のいく住宅ローンを組みましょう。
借り換えという方法もありますが、一般的には借り換えずに支払っていく方がほとんどなので、長い期間返済することを考えると信頼できる金融機関を選ぶようにしてください。 -
「こどもみらい住宅支援事業」について解説します!
- 投稿日

こんにちは!名稲建設株式会社扶桑展示場です!
2021年11月26日に閣議決定された「こどもみらい住宅支援事業」について、気になる人も多いのではないでしょうか。
自身の家を建てる時にこうした制度が利用できるのかどうかは、とても重要な部分なので理解しておくと便利です。
今回は、こどもみらい住宅支援事業についてご紹介していきます。ぜひ参考にしてみてください。こどもみらい住宅支援事業って何?
こどもみらい住宅支援事業は「子育て世帯の支援」を目的とした住宅補助金制度です。
さらに、現在世界中で注目されている2050年カーボンニュートラルを実現しよう、という観点から「高い省エネ性能を有する新築住宅の取得、省エネ改修」に対して補助されます。補助対象や期間など、詳細をご紹介します。補助の対象や金額
補助対象者は、以下の通りです。
・18歳未満の子どもを持つ子育て世帯(年齢は令和3年4月1日時点。すなわち平成15(2003)年4月2日以降出生)
・夫婦どちらかが39歳以下の若者夫婦世帯(年齢は令和3年4月1日時点。すなわち昭和56(1981)年4月1日以降出生)
・対象工事を実施するリフォームでの申請は全世帯最大補助金額は、大きく分けて以下の3つです。
・ZEH、 Nearly ZEH、 ZEH Ready 又は ZEH Oriented の場合:100万円/戸
・高い省エネ性能等を有する住宅:80万円/戸
・一定の省エネ性能のある住宅:60万円/戸リフォームの場合は、上限30万円/戸ですが、子育て・若者夫婦世帯の場合は上限45万円/戸もしくは既存住宅購入を伴っていれば上限60万円/戸といったように、子育て・若者夫婦世帯にとっては特に良い制度です。
詳しい条件などは下記資料にてご確認ください。(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001444200.pdf)
補助の対象期間
補助の対象期間は、注文住宅を購入・リフォーム、新築分譲住宅の購入のいずれかによって少し変動します。対象期間は申請する際にとても重要になるため、覚えておきましょう。
①注文住宅購入・リフォームの場合
工事請負契約が契約変更を除き、2021年11月26日〜2022年10月31日までに締結したもの。また、事業者登録を行なった後、2022年10月31日までに建築着工するもの。ただし、申請の際に工事が一定以上の出来高に達しており、期間内に申請・完了報告が可能なものに限る。
【申請時期】
注文住宅:補助額以上の工事が完了後
新築分譲住宅の購入:補助額以上の工事が完了後
リフォーム:全ての工事が完了後②新築分譲住宅購入の場合
新築分譲住宅の場合も、建築着工に関しては注文住宅を購入・リフォームの場合と同じ期間です。また、2021年11月26日〜2022年10月31日までに売買契約したものも対象となります。
手続きについて
手続きに関しては、購入者である一般消費者が何か申請するということはありません。
工事を行う事業者や販売事業者が申請手続きをするものなので、もしも自分が依頼する業者がこどもみらい住宅支援事業の事業者登録を行っていない場合は、補助の対象とはならないので、十分に注意しましょう。
手続きは事業者に行ってもらいますが、申請をするにあたりきちんと購入者にも説明を行い、還元方法について予め両者で同意を行うという決まりがあります。
この点は、十分に意識しておかなければならず、こどもみらい住宅支援事業制度について理解していても、こうした細かな部分の把握はできていないことも多いので注意しましょう。
そのため、こどもみらい住宅支援事業制度を利用したい場合は、業者に依頼する前に依頼しようと思っている業者が登録事業者なのかも確認しておくと良いです。
こどもみらい住宅支援事業の事業者登録期間は、2022年1月中旬から遅くとも2022年10月31日までが予定されています。注意点
こういった補助金制度は期間内であれば、いつでも大丈夫とイメージする人も多いですが、こどもみらい住宅支援事業の場合は予算が決められています。
そのため、予算上限に達した場合は申請期限内だったとしても早期終了する可能性があるので、住宅購入もしくはリフォームを検討している人は早めの行動が吉です。補助対象となる具体的な要件
補助対象となる要件をよく理解しておきましょう。
子育て世帯、又は若者夫婦世帯
子育て世帯というのは、申請の時点で18歳未満の子供がいる世帯のことを指しています。
若者夫婦世帯というのは、申請の時点で婚姻関係にあり、夫婦どちらかの年齢が39歳以下の世帯を指しています。
子育て世帯、若者夫婦世帯どちらも年齢は、2021年4月1日時点でという点がポイントになります。
生命保険でもそうですが、年齢というのはこうした制度にとって非常に重要なポイントでありながら忘れがちな部分なので、注意しましょう。住宅の性能
こどもみらい住宅支援事業は、世帯の応援の他にも環境に優しい住宅づくりも支援しています。具体的にどのような住宅が補助対象になるのかご紹介します。
①ZEH住宅
ZEH住宅はNet Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略です。
分かりやすく言うと、エネルギーを作り出す家のことを指していて、他からのエネルギーを極力必要としない住宅のことを指しています。
こどもみらい住宅支援事業で、もっとも補助金が多いタイプの住宅です。ZEH住宅は「省エネ・創エネ・断熱」が基本で、暖房や給湯などの設備などは燃費が良いものなどを使用していると該当します。さらに、ZEH住宅でも種類が分かれていますがそれら全てが補助対象となるのでよく覚えていましょう。
※ BELS 評価書に記載される「ゼロエネ相当」(強化外皮基準に適合しないもの)は対象になりません。②高い省エネ性能等を有する住宅
わかりやすく言うと以下の3つの住宅を指しています。
・長期にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられた優良住宅である「認定長期優良住宅」(例:耐震対策、バリアフリー対策など)
・二酸化炭素の排出を抑制する建物で所管行政庁が認定している「認定低炭素住宅」(例:節水設備、雨水や井戸水利用の設備、ヒートアイランド対策など)
・建築物省エネ法第35条に係る「建築物エネルギー消費性能向上計画」の認定が基準に適合していると所管行政庁が認定している「性能向上計画認定住宅」
言葉にするとかなりややこしく感じられますが、簡単に言いかえると「不必要にエネルギーを使わずに過ごしやすい家づくりがされているのか」ということです。断熱性があれば冬は暖かく、夏は涼しく過ごすことができますし、燃費の良い設備を使えば節約にもなります。快適な住まいづくりに役立つので、省エネ性能を有する住宅はこれから家を建てる人に注目されています。③一定の省エネ性能のある住宅
法律で定める断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅が該当します。この場合は、最大補助金額は60万円/戸の対象になります。
そのほかの補助金と併用可能?
こどもみらい住宅支援事業と補助対象が重複する補助金制度については原則併用はできません。しかし、一部補助金と併用できるものも存在しているので当てはまるかどうか確認しておきましょう。
すまい給付金
消費税率引き上げによって、住宅取得する人の負担を緩和するための制度です。収入額によって判断され、最大50万円まで給付されます。給付対象は、引き上げ後の消費税率が適用・床面積50㎡以上・第三者機関の検査を受けた住宅であることです。ただ、このほかにも新築住宅を購入したのか、住宅ローンは利用しているのかによって要件が多少異なります。
住まいの復興給付金
消費税率の引き上げにより、東日本大震災で被災した方の住宅再取得や補修にかかる負担を軽減する制度です。
外構部の木質化対策支援事業
規定の保存処理木材を使用することで、工事費用を補助してもらえる制度です。堀の場合は最大3万円、デッキの場合は最大15万円給付されます。
似たような補助金制度でも、以下の制度はこどもみらい住宅支援事業との併用はできません。
・地域型住宅グリーン化事業
・ZEH支援事業
・ZEH化による住宅における低炭素化促進事業まとめ
こどもみらい住宅支援事業についてお伝えしました。
制度の名前の通り、これからの日本を支えていく子育て世帯、又は若者夫婦世帯が対象となるため、自身で新築住宅を購入することを不安視していた人でも補助金を受け取ることによって、少し不安は払拭されるでしょう。
注文住宅・新築分譲住宅の購入だけではなくて、リフォームでも補助の対象になるという点が大きなメリットといえます。
家は長い年月を過ごすことになる場所なので、家族で快適な住まいを手に入れるためにもこどもみらい住宅支援事業は利用を検討すべき制度です。高性能で省エネな住宅実現のためにも、制度の活用が重要なポイントになります。 -
ライフ・パートナーズ Vol.57
- 投稿日


-
火災保険は必要?加入の際のポイントを紹介!
- 投稿日

こんにちは!名稲建設株式会社扶桑展示場です!
注文住宅の検討を進めていく中で、火災保険について営業担当から話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。言葉は聞いたことあるものの、詳しい内容は分からないという方も珍しくありません。そこで、今回は火災保険の必要性や加入の際のポイントについて紹介していきます。さらに、損害保険料率算出機構の火災保険参考純率の引き上げに伴う変更点についても解説していきます。火災保険とは?
火災保険とは、居住している建物が火災に遭った際の損害を補償してくれる安心の保険です。さらに、火災による損害だけでなく、自然災害なども対象となっており、住居に関わる様々なトラブルにも対応しているのが特徴です。ただし、保険内容によって条件や対象範囲が異なるため、加入前には内容をよく確認することが大切です。また、保険の種類や保険会社によって保険料が異なるため、どのような種類の保険が必要なのか、保険料はどのくらいが相場なのかを確認しておきましょう。
火災保険の見直し
損害保険料率算出機構は2021年5月21日付で火災保険参考純率を全国平均で10.9%に引き上げる届けを金融庁に提出し、2021年6月16日付で正式に受領されました。
損害保険料率算出機構とは国内の様々な損害保険の参考純率や基準料率などをシミュレーションしており、多数の保険会社に共有している機関です。複数の保険会社の事故事例や補償事例などを計測し、参考となる純率や保険料率をシミュレーションすることで、参考保険相場を保険会社に提供しています。そして、損害保険料率算出機構が2021年5月に火災保険参考純率を引き上げる旨を金融庁に提出したことから、来年度から保険料率などの見直しが図られることが予想されます。
※今回の改定内容を採用するか否かは各保険会社が判断更には、最終的な保険料、改定した保険料の販売時期は、各保険会社の判断で決定されます。 参考純率とは
保険料率は純保険料率と付加保険料率で構成され、損害保険料率算出機構では純保険料率部分を算出しています。
当機構が算出する純保険料率を「参考純率」といいます。
当機構の会員となっている保険会社では、参考純率をそのまま使用することができ、また、自社の商品設計等に応じて修正して使用することもできます(参考純率は使用義務のない参考数値であり、これを用いずに保険会社独自に純保険料率を算出することができます)。純保険料率に保険会社で算出した付加保険料率を加えたものが、契約者が負担する保険料率となります。
当機構で行う改定内容を採用するか否かは各保険会社が判断します。したがって、最終的な保険料は各保険会社の判断で決定される点にご留意ください。
また、保険会社が自社の保険商品に参考純率を使用する場合においても、販売時期は保険会社が決定
します。
さらに、東京海上日動火災保険株式会社では、来年2022年10月1日以降始期日契約から、引き受け可能な保険期間が最長5年に短縮となる予定です。改定の背景は、自然災害リスクは将来にわたり大きく変化していくと見込まれ、長期的なリスク評価が難しくなっているため。これを受けて、参考純率に沿った改定を行う方針となりました。
※保険期間最長5年の短縮は今後認可をとるものなので、最終決定事項ではないことをあらかじめご承知おきください。
火災保険参考純率見直しの背景
火災保険参考純率が見直されるきっかけとなったのが、自然災害リスクの増加です。
損害保険料率算出機構では過去4年間の火災保険の支払い実績を計算し、年々増加傾向にあることを指摘しています。たとえば、2017年度の支払保険金は1,378億円でしたが、2020年度では7月の豪雨災害で848億円、台風10号で932億円まで増加しました。さらに、2019年の台風15号、19号の影響により、それぞれ4,000億円以上の火災保険が支払われたというデータが残っています。
そして、築年数の古い住宅が増えてきていることも、火災保険参考純率引き上げのきっかけとなっています。日本国内では、築10年以上の住宅が占める割合が2015年に65.8%だったのが、2019年には72.1%になっています。築年数が古い住宅は新しい家と比べて、倒壊リスクが高くなるだけでなく、火災や水漏れなどの影響を受けやすいとされています。そのため、今後の被害リスクを考慮すると、火災保険参考純率を上げることが必須となってきているのです。火災保険が必要な理由とは?
保険料率が上がることが予想されている火災保険ですが、そもそも火災保険に入らなくてもいいのでは…と考える方もいると思います。
しかし、結論から言えば火災保険は加入した方がよいです。
なぜなら住宅の修理や修繕は高額になってしまうからです。火災保険は様々な被害に対応しているものが多いので、安心して日々の暮らしを送るためにも火災保険には加入することをお勧めします。万一の事故に備える
火災保険と聞いて、第一に思い浮かべるのが「火災」。
注意をして生活していても、隣家からもらい火を受けてしまってはどうしようもありません。さらに、もらい火の場合、隣家(出火元)に重大な過失がなければ、賠償責任が発生しないという特徴があります。つまり、隣の家から火が燃え広がったとしても、過失がなく事故で火災が発生してしまった場合は隣の家に賠償責任を問うことができません。そのため、たとえ家を失ったとしても、誰も保証してくれず、自分でなんとかしなければならないのです。
しかし、火災保険に加入していれば、もらい火であってもしっかりと補償してくれます。さらに、保険の種類によっては仮住まい費用を負担してくれることもあり、新しい家が完成するまで安心して生活を送ることができます。加入義務がある場合も
最近の家は耐火性にも優れているため、簡単に火が燃え広がるということはありません。しかし、万一の火災に備えておく必要はあります。さらに、住宅ローンを利用して注文住宅を建てる場合はローン契約時に火災保険の加入が義務付けられていることもあります。
この理由は、住宅ローンの契約期間の長さに関係しています。通常、住宅ローンは20年や30年、35年など長い年数で返済していくものです。長期間の返済中に何らかの被害を受けてしまうと、返済が苦しくなったり、住宅の価値がなくなったりしてしまうことがあります。たとえば、住宅が火災によって全焼してしまった場合、住宅の価値はなくなってしまいますが、住宅ローンは残り続けるのです。そこで、住宅ローンを扱っている金融機関では火災保険の加入を義務付けており、万一の火災などでも、住宅の価値を担保できるようにしているのが特徴です。住宅ローンでは住宅そのものを担保にしていることが多いため、火災や自然災害などで住宅の価値を失ってしまっては、金融機関にとっても大ダメージなのです。
そのため、住宅ローン契約時は利用者に火災保険の加入を義務付けていることが多いです。火災保険を選ぶポイントとは?
加入の必要性が高い火災保険ですが、ここでは火災保険を選ぶポイントについても紹介していきます。
複数の業者から見積もりを取る
火災保険を検討する際は複数の業者から見積もりを取るようにしましょう。
火災保険は保険会社や種類によって保険料や補償内容が大きく異なります。そのため、可能な限り複数の保険会社から見積もりを取り、条件に合った火災保険を選ぶようにしましょう。補償内容を確認する
契約前に補償内容を確認しましょう。万一に備えるのが保険です。しかし、いざ保険を利用しようとすると、補償の対象外だったということも珍しくありません。そうならないためにも、契約前に必ず補償内容を確認しておきましょう。
たとえば、自分の過失で火災を起こした場合は補償されるか、地震によって火災が発生した場合は補償されるか、など様々なケースを想定して内容を確認することをおすすめします。気になることはどんどん質問し、しっかりと補償内容を確認することが大切です。まとめ
注文住宅を検討する中で火災保険の検討も併せて進めていくことが多いです。火災保険は火災による損害を補償するだけでなく、自然災害にも対応していることが一般的です。しかし、契約前にしっかりと内容を確認しておかないと、いざ利用しようとした時にトラブルになることも。したがって、契約前に複数の保険会社から火災保険の見積もりを取り、それぞれの内容を確認した上で、契約するようにしましょう。